今月の特集題 礼拝の充実を目指して
賛美にあふれて
今月の特集題 礼拝の充実を目指して
賛美にあふれて
![]()
| 鈴木 恵子 |
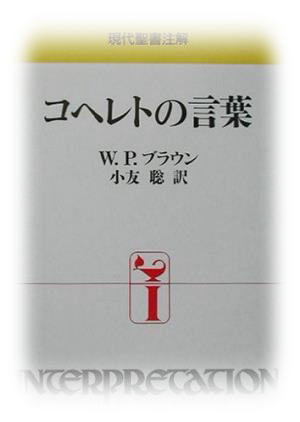 「追いやられたものを、神は尋ね求められる。」 「追いやられたものを、神は尋ね求められる。」(コヘレトの言葉3章15節) 神は人間をこよなく愛し、ご自分の息を人に吹き込まれた。私たち人間は神と息を通わす存在とされた。しかし、人間は神を忘れ、自分本位に生き、その結果、全ての被造物の呻きを招いてしまった。弱い者の涙は枯れず、罪は身の丈を超えた。このままでは全員が滅びの闇に投げ込まれる。 神はご自分に似せて創られた人間に哀惜の情をもって、慈しみ追い求めてくださった。この神の追いかけが、ついに、御子イエス・キリストとなって、この世に現された。御子の誕生である。ハレルヤ。 この御子の誕生がなければ、イエス様の十字架の贖いがなければ、復活と昇天がなければ、私たち人間は未だ闇の世に呻きながら希望もなく空しく生きるのみであった。 今、夕礼拝でコヘレトの言葉を学んでいる。コヘレトの言葉の著者は、伝統的にはソロモンと言われ、神を畏れる賢者である。しかし、残念なことに、彼には主イエスの救いと復活の永遠の命の存在が隠されていて、死んだら全てがお終いである。故に、この世の出来事は彼にとってはみな空しく風を追うようなものだと嘆く。彼が見た世には真の救いも慰めもなく、生きる苦しみばかり。ならば、生まれてこないほうが良かったとまで嘆く。主イエスのいない世界は闇である。その闇を彼は語っている。  今は救いの時、恵みの日。主イエスの十字架の贖いを受け、復活の希望の道を指し示されている。なんという幸いな時に生れたことよと思う。主イエスが共にいなければ、彼と同じように、嘆く一生であった。主イエスが共にいなければ、次々と遭遇した艱難、悲しみを乗り越えることは出来なかった。主イエスが共におられるので、弱くても強くされた。主イエスに全て委ねる生活の解放感と平安は他に譬えようがない。 今は救いの時、恵みの日。主イエスの十字架の贖いを受け、復活の希望の道を指し示されている。なんという幸いな時に生れたことよと思う。主イエスが共にいなければ、彼と同じように、嘆く一生であった。主イエスが共にいなければ、次々と遭遇した艱難、悲しみを乗り越えることは出来なかった。主イエスが共におられるので、弱くても強くされた。主イエスに全て委ねる生活の解放感と平安は他に譬えようがない。この原稿の締め切り日は、記憶に間違いがなければ、待降節に入る日だ。私たちは待ち望む。心から待ち望む。しかし、私たち以上に待ち望まれているお方がある。父なる神様が私たちを待ち望んでおられる。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るように、両手を差し伸ばし待ち望んでおられる。このように、待ち望むお方があるからこそ安心して私たちは神に向かって、力強く歩みだすことが出来る。 「ハレルヤ。主の僕らよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに、主の御名がたたえられるように。日の昇るところから日の沈むところまで、主の御名が賛美されるように。」 (詩編113編1〜3節) どんな時でも何時でも、賛美しましょう。 |
| (すずき けいこ) |
| 舟橋 葉子 |
越谷教会の礼拝堂に響く讃美歌には、心が洗われる思いがします。力強く喜びに満ちた歌、静かに主を見上げる歌。その旋律には歌い手ひとりひとりの信仰が込められています。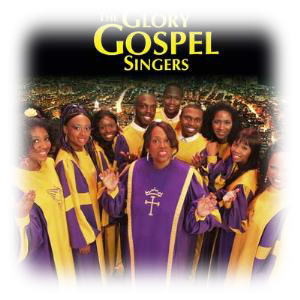 教会の外でも、神様を賛美する歌はたくさん歌われています。さまざまな歌がありますが、代表的なものはゴスペルソング、略してゴスペルでしょうか。教会が主導してゴスペルサークルを立ち上げた例があります。ゴスペルを通して教会に興味を持って欲しかったのですが、サークル参加者は多かったのに礼拝に繋がらず「失敗だった」と消滅してしまいました。またきちんと活動しているものの、メンバーの中にクリスチャンが一人もいないというサークルもあります。 教会の外でも、神様を賛美する歌はたくさん歌われています。さまざまな歌がありますが、代表的なものはゴスペルソング、略してゴスペルでしょうか。教会が主導してゴスペルサークルを立ち上げた例があります。ゴスペルを通して教会に興味を持って欲しかったのですが、サークル参加者は多かったのに礼拝に繋がらず「失敗だった」と消滅してしまいました。またきちんと活動しているものの、メンバーの中にクリスチャンが一人もいないというサークルもあります。はたして信仰の歌を、信仰なしに歌うことは許されるのでしょうか。歌うことは可能ですが、それはあるべきゴスペルの姿なのでしょうか。ゴスペルの話になると、必ずといってよいほどこの疑問が出て来ます。 ゴスペルシンガー塩谷達也さんの著作「ゴスペルの本」によると、ゴスペルサークルの参加者に対し「クリスチャンとしての信仰を持っていないと、ゴスペルを歌えないと思いますか?」という質問をしたら、回答は「その通り」が8%、「そうは思わない」が83.5%でした。「思わない」が圧倒的多数ですがおそらくこの回答者はノンクリスチャンが多かったでしょうし、また数字に表しきれない要素が、グラデーションのように含まれているように思えます。 概ねクリスチャン側の意見は、ぜひ信仰心を持って歌いたい、そうでない場合でもいつかは信仰に至る道として捉えたいというものです。信仰がなければゴスペルとは言えないという厳しい考えもあります。 それに対してノンクリスチャンの考えは多種多様です。歌ったときに感じる充足感を、信仰へのきっかけと受けとる人もいますが、音楽としての魅力と信仰は無関係とする立場もあります。その間にあって受洗はしていないが信仰への敬意はある、また歌詞を理解して歌う努力をするという方々が多数派であろうと思います。  それらの全部を包括してゴスペルが歌われ神様に差し出されます。神様は喜んで受けとってくださるのではないでしょうか。 それらの全部を包括してゴスペルが歌われ神様に差し出されます。神様は喜んで受けとってくださるのではないでしょうか。最初に、礼拝の讃美歌には信仰が込められていると書きましたが、まだ信仰の確信に至っていない人、気持ちが揺らいでいる人、あるいは習慣で声を出しているだけの場合もあるかもしれません。それでも、神様はその人それぞれの時を祝し、いつか賛美する意味を実感できる時への準備としてくださるのだと信じます。 |
| (ふなはし ようこ) |
| 越谷教会月報みつばさ2016年12月号特集 「賛美にあふれて」より |