今月の特集題 熱心に語る
![]()
| 薩摩 雅宏 |
 「熱心に語る」という特集で今回の依頼を受けました。CSの校長ということが多分にあると思います。まぁ、職業柄も熱心に子どもたちに話さなくてはいけないこともあります。 「熱心に語る」という特集で今回の依頼を受けました。CSの校長ということが多分にあると思います。まぁ、職業柄も熱心に子どもたちに話さなくてはいけないこともあります。新米教師の頃、授業中に黙っていることに我慢できないことが多かったです。例えば、3分間黙っているといけません。いや、1分間でも駄目です。つい、何かを言ってしまうのです。算数の問題を解くのに3分間与えて、子どもたちが真剣に問題を解いているのに「ヒント〜」とか言って話してしまうのです。 しかし、教師を重ねるにつれ、黙っていられる時間が伸びていきます。今なら、1時間は大丈夫(それでは、授業じゃないって?)。子どもに任せるということができるようになったのです。これは、子どもを信頼していなければできないことです。CSでも同じことがいえるでしょう。子どもに向かって子どもと神様を信頼して話すことが大事だと思うのです。 私がCSの教師に成り立ての頃の話です。教師には、説教の参考に教師の友が配付されます。その中には、その聖書の箇所の説教例が記載されています。それを参考にすると、お話を作りやすいのです。しかし、時としてその参考例に首を傾けてしまうこともあるのです。そんな時は、どうしたらいいのでしょうか?それを解決してくれたのが当時校長先生だった長尾弘先生のお話です。「何を語るか、聖書の語る言葉を良く読むことだよ。教師の友を読む 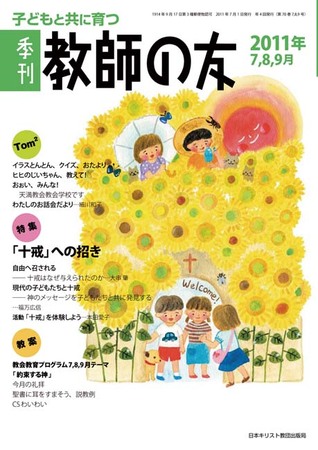 前に聖書をしっかり読まなければね」。そうです。子どもたちに何を語るかは、聖書の御言葉なのです。教師の友の参考例を語るのではないのです。長尾先生の話を聞いてから、私は聖書を語ろうと決めたのです。教師の友は、参考程度にして。ここ最近は、教師の友の説教例を話したことはありません。自分の言葉で、聖書を語るようにしています。 前に聖書をしっかり読まなければね」。そうです。子どもたちに何を語るかは、聖書の御言葉なのです。教師の友の参考例を語るのではないのです。長尾先生の話を聞いてから、私は聖書を語ろうと決めたのです。教師の友は、参考程度にして。ここ最近は、教師の友の説教例を話したことはありません。自分の言葉で、聖書を語るようにしています。ここで、また小学校教師の話。「よい話し手になるには、よい聞き手にならなければならない」と言われます。だから、学校では教室に「聞き方名人」という掲示物が前の方に貼られています。相手の話を聞くではなく、聴くのです。耳と目と心を使って聴くのです。御言葉を語る者もまず、聴く者とならなければなりません。聖書を開き、じっくりと読み、祈り、神様に聴くことがまず必要です。そして、熱い想いを持って御言葉を話していくことが求められます。足りないところは神様におまかせして。いろいろな思いで教会学校に来る一人一人に語りかけていくのです。 |
| (さつま まさひろ) |
| 棚橋千恵美 |
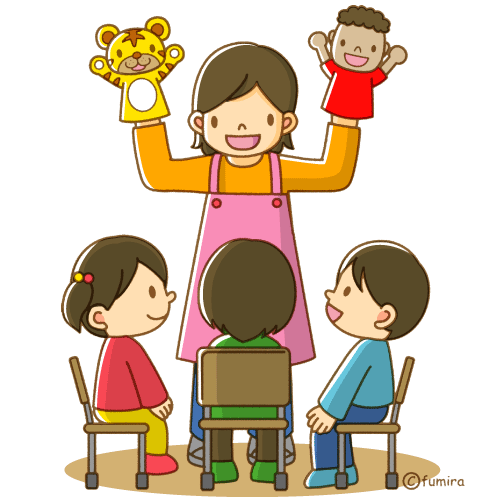 今年の越谷教会の伝道主題『行け。わたしがあなたを遣わす』との御言葉から、「熱心に御言葉が語られ、熱心に御言葉が聞かれ、熱い礼拝を献げ、この礼拝で熱くされた心を持って証し人として地域に出て行くものでありたい」と示されました。石橋牧師は「熱く御言葉を語れ!」と命じます。「幼稚園の財務全般任せているから」とも言われます。越谷教会への招聘は、幼稚園財務担当を含めてのことでした。財務全般には、それに関連、付随して内容は多岐にわたります。「子どもと遊べ!」とも言われます。「遊ぼうよ!」と誘ってくれる子どもたちがいます。「遊ぼうよ!」と誘われたら、忙しくても緊急でない限りホイホイ喜んでついて行き、遊んでもらって時間が過ぎて、だけど、仕事は片付いて行くのです。わたしの「忙しさ」の根拠はどこにあるのでしょう? 今年の越谷教会の伝道主題『行け。わたしがあなたを遣わす』との御言葉から、「熱心に御言葉が語られ、熱心に御言葉が聞かれ、熱い礼拝を献げ、この礼拝で熱くされた心を持って証し人として地域に出て行くものでありたい」と示されました。石橋牧師は「熱く御言葉を語れ!」と命じます。「幼稚園の財務全般任せているから」とも言われます。越谷教会への招聘は、幼稚園財務担当を含めてのことでした。財務全般には、それに関連、付随して内容は多岐にわたります。「子どもと遊べ!」とも言われます。「遊ぼうよ!」と誘ってくれる子どもたちがいます。「遊ぼうよ!」と誘われたら、忙しくても緊急でない限りホイホイ喜んでついて行き、遊んでもらって時間が過ぎて、だけど、仕事は片付いて行くのです。わたしの「忙しさ」の根拠はどこにあるのでしょう?「熱く語る」この主題で何を書けば良いのか途方に暮れました。説教者は、御言葉を熱心に語ることが務めです。当然、分かり切ったことを説教者としてどう書けば良いのか途方に暮れて、石橋牧師に助言を求めました。「わたしは御言葉を熱心に語れません!」「熱心ではなく、死にもの狂いだと書けばいい!幼稚園の仕事をしながら、死にもの狂いで説教に取り組んでいると書けばいい!」。ありがたい助言でした。 月曜日、「説教の準備をしなければ」の声が聞こえ、週末に近づくにつれてその声は次第に大きくなって、金曜日の夜には「暗雲」となります。この「暗雲」は、翌日の土曜日には「暗闇」になるのです。土曜日深夜になっても、「原稿」真っ白!「気持ち」真っ暗! 幼稚園の仕 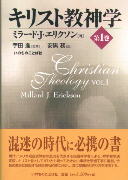 事との兼ね合いで忙しいのは事実です。説教の準備を始めよう・・神学書、注解書を拡げて時間をかけたその努力の結果、机の上は本の山。本の山に聖書が埋もれることがある。神学書の山積はわたしの成し得る努力に違いないけれど、肝心の聖書を埋もれさせてどうするの?わたしは一体何をしているのでしょう?努力の果てに聖書から響く神の言葉がある。「説教準備」の仕切り直しが始まるのです。忙しいから死にもの狂いなのではありません。神の言葉が響かない、分からない、時間がない、間に合わない!だから、死にもの狂いなのです。わたしは御言葉を熱く語れません。御言葉を熱く語るために死にもの狂いなのです。 事との兼ね合いで忙しいのは事実です。説教の準備を始めよう・・神学書、注解書を拡げて時間をかけたその努力の結果、机の上は本の山。本の山に聖書が埋もれることがある。神学書の山積はわたしの成し得る努力に違いないけれど、肝心の聖書を埋もれさせてどうするの?わたしは一体何をしているのでしょう?努力の果てに聖書から響く神の言葉がある。「説教準備」の仕切り直しが始まるのです。忙しいから死にもの狂いなのではありません。神の言葉が響かない、分からない、時間がない、間に合わない!だから、死にもの狂いなのです。わたしは御言葉を熱く語れません。御言葉を熱く語るために死にもの狂いなのです。原稿締切、大幅に遅れて本当に申し訳ありません。「みつばさ」の原稿を書いているこの朝は金曜日。間もなく暗雲が広がります。またしても、暗闇の土曜日がやって来る。熱く御言葉を語りたい・・・。わたしの死にもの狂いの道のりはいつまで続くのでしょう。 |
| (たなはし ちえみ) |
| 越谷教会月報みつばさ2012年6月号特集「熱心に語る」より |